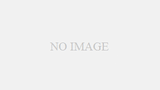「○○県が50歳代の男性職員2人を、地方公務員法に基づき、『能力不足』として分限免職処分にしていたことが分かった。▽業務の指示に従わない▽資料を紛失する▽数日でできる仕事に3か月かかり、仕上がりもよくない――といった勤務態度だった...。県人事課」と、○○新聞報道。
なんと! これは...“幼さ”かナ...? この“幼さ”が、昨今あちこちで様々な災いを起こしていると言えそう...。
まず、県庁人事課はこれを公表する意義があったの? 当該職員さんは50歳代とのこと。それなりの職歴を経て人生を重ねて来られた方々。状況的には、心身の疲労も表われてくる年齢。加えて、業務形態は日々にデジタル化し、それに歩調を合わせた対応が求められる。私生活においても様々に問題を抱える年齢でもある。機械ではない生身の人間なのだ。
心理的な要因があるのかもしれない。その辺りを傾聴して話し合った結果、本人の同意を得た上で方向決定されることが望ましいが、そのような親身な対応があったのだろうか。
「能力がない」というのは大ナタを振り下ろすほどの殺傷感があり、身も蓋もない。ご当人たちは生きてゆかねばならない。まだまだ人生は続く。“犯罪者”ではないのだ。
このプライベートな事案を公に晒すのは「人権侵害」に等しい。どんな権利を行使してこの横暴さに至るのか。そして、これを報じた地方新聞。さらにそれを転載した大手新聞社。 「県庁」は今や時の組織。話題性があれば何でも…。 県の宣伝も兼ねてこの風潮に乗ったかと疑いたくもなる。
能力というけれど、人はそれぞれ考え方、思考回路が違っており、型にはめることは決してできない。おそらく本人さえ気づいていない能力も持ち合わせているはずの当人の能力を、その一端を見て他人が評定することに非情な“暴力”が感じられる。同時に評定者の未熟さも同程度に伝わってくる。
余談だが、その昔、数学の公式に沿って解く問題の前で戸惑っている生徒がいた。手順さえ踏めば正解は導けるのだが、真意の読めない質問を繰り返している。周りは不思議そうに半ばあきれ顔。ところが、数日後に応用問題を解けたのはその生徒だけだった。
場合と必要に応じて「教え方」というものがある。当人の「思い込みの壁」に阻まれて能力が開花できないでいる場合もある。基本は、動けないでいる“障害”に気付かせて当人の本来の力に目覚めさせる。そうすれば当人は嬉々として能力を開花し始める。
学習の場でも福祉の現場でも...おそらくあらゆる場面において、これは人の補助の基本であると考えている。
そして、思うのは、どんな組織でも上位の立場にある人は、躓いている人にこの方法で対処してほしい、と。
特に、職場では「やる気」が強調されるけれど、無理なくそれを引き出せるのはこの方法であることは確かだ。そこに内在するのは「思いやりと信頼」のようだ。。