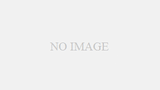「そういう声は一件も届いていません」これが第一声だった。 購入取付したばかりのエアコンが耳障りな音を発している。電源を切った後に訪れる安らぎと安心感。 不可解ながらも、対策を求めてとりあえず販売店へTelした。メーカーの相談部署に取り次いでくれることを内心期待しながら。ところが、話の最中に上記の言葉が何度も繰り返されて、対応不可との回答。
このパターンは多い。すぐさま防御態勢となり、それを強化するために訴えを暗に否定する言い方となる。”苦情”ととるか”相談”ととるか、そこには電話対応した個人の知性と判断力が表れる。 やりとりがどうあろうとも、訴えの主旨をつかんでほしい。経験上、不思議にこの点がおろそかになりがちなのだ。この場合、会話の中で求められているのは「解決」である。なので、結局こちらから誘導することとなった。「メーカーの相談窓口の連絡先を教えてください」。 難しいことでは決してなかった。「そういうことでしたら、メーカーの修理相談に連絡してみてください。こちらの方では機能については対応しかねますので。連絡先をお伝えします・・。保証期間内ですから費用はかかりません」と、それだけで事は済んだのだけれど...。
特に驚いたケースではこんなことがあった。 今販売されている使い捨てライター。点火にかなりの力を要するため親指が故障してしまった。 子供対策も含めて発火し易さを減じるために、対策として点火規制が設けられてからずいぶん経つ。しかし、昨今わが身にあきれながらも、改めてライターの点火にこれほどの力が必要だったのかと驚く。身体機能が低下する利用者のことも考慮してはどうかと考えた。 規制緩和をしてほしいな、と思いつつライターの記載先に苦情を兼ねてTelしてみた。 「所管してるところはどこですか?」 と問う。 「消費者センターに訊いてください」 (ここでびっくり‼) 「そこ(あなたの今いる所)は会社ですか?」 (周りに社員がいますか?) 「そうです」 「では、他の人に訊いてみてもらえませんか?」 (対処の”いろは”ですけど、どうしたの?) 待たされて返された答えは不機嫌そうな「経済産業省」のひと言。お詫びの言葉などない。 このような例は近年珍しくないかもしれない。悪びれた様子がまったく感じられないことにさらに驚いたものだ。
牽制し合っているのかナ?それぞれが。そんな社会の空気だ。 敬語にもならない言葉を、丁寧そうに言いさえすればそれが立派な通行証ででもあるかのような場面に社会は満たされているけれど、この寒々しさたるや...。 ハードなカスタマーハラスメントはこんな情勢を反映したものかもしれない。
かつて、輸入菓子の販売会社にいたことがある。苦情処理も言い遣って、代替商品を苦情者のお宅まで届けたことがある。 「クッキーが湿気っている」と、買主からの電話。そこで若干のやりとり。 「では、送ってもらえませんか」最終手段として営業責任者が回答する。 送られてきた缶の中にはわずかに残ったクッキーが入っていた。 営業責任者は大笑いしながら、「届けに行って」と丁寧に包装した新品を手渡して命じた。電車で一時間以上かかる場所だった。 ”カスハラ”云々の話を聞くたびに、遠い昔のこの営業責任者の対応がなつかしく思い出される。人間味があった。 暖かだった。 あの頃、平和だった。