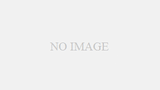新潟産“コシヒカリ”、いつもの5㎏1,800円が、4,000円以上になっていた! スーパーに行く度にモノが値上がって止まらない上に、何事...⁉
これではかつてのあの「米騒動」前夜と同じ状況だ。諸物価とくに米価の暴騰が、大正時代のあの「米騒動」の発端となった。 で、今、この有様。
米不足か?と思いきや、何やら怪しげな情報が出回っている。
「農林中央金庫が資金投資で1.5兆円の損失補填をしたために日本米を米・中等に大量輸出している」等。それを裏付けるように、米国の店頭でやたらと日本米が目につくとの情報も多く見受けられる。因みに日本米はブランド化されて海外では高く売れるそうだ。
が、これらの情報の真偽のほどは不明。
というのは、昨年の輸出量は前年を上回る生産量の0.54%に過ぎないという主張も一方にある。
これからどうなっていくの? モノの値段は日々高くなり、輸入品ばかりで自国の生産物が食べられなくなる?
この不安に拍車をかけるのが「食料供給困難事態対策法」。この4月から施行。
「異常気象による食糧危機」に備えて(「国際情勢の危機に介入する可能性に備えて」じゃない?) 農家に生産拡大を要請し、増産計画の届け出を指示できる(「支持する」)新法が昨年6月に可決、成立した。
全閣僚が対策本部設置。政府が供給目標を定め、農家へ増産要請、輸入業者に輸入拡大を求めてその計画作成を指示できる(「指示する」)。米、小麦、大豆などを対象とする。
時代錯誤的な不気味な有事法制だ。
<農業従事者の心情>『実効性がどれだけ担保されているか、現状を見る限り、その余力が全くない。平時の生産基盤をしっかり充実させ、確保させていくということがあってこその法制だ』 『お前、平時はこんなにしておいて、困っている時に助けてくれと言われても、それはおいそれと乗れない』。
当然ですよね~。
こんな事態になって改めて自覚を深めるのは、自分たちは第一産業に養われているという事実。 これは最重要認識なのに普段忘れている。生き方の“原型”なのに。
災害その他のいわゆる有事に遭遇した時、生きるに必要なものはまず、食物、水。
この肝心な育成供給に従事する人たちを、国は、政府は、歴史上の権力者たちはどんな風に処遇してきたか?「百姓」と侮蔑を込めて軽んじてこなかったか。もしそうなら、とんでもない心得違いだ。先祖に向かって、天に向かって唾を吐くような愚かしい心根。
水を引いて大地を耕し、作物を作る人たちがこの国を養ってきた。誰もがその手で、その恩恵を蒙って生きてきた。そして今も続く。
国は彼らを重用してきたか?この産業に重きを置いてきたか? まず、そこを正してほしい。
そしてまた、業務に携わったことのない人間が、この法律でどんな主導ができるのか?
『今回の法律は、農業を知らない人が作ったのかな、というのが僕の感想だ』と、就農25年の現役者の声もある。
総体的に「社会的意識の偏り」どころか、まるで方向が違っている。
生きる“原型”を豊かに保ってこそ、土地の住民(国民)は本来の生を体感できる。 ここを押さえておいてほしい。
一般的に、そもそも「大切なもの」は何か、という評価、基準が引き起こす社会的問題が多く目につく現代ではある。
「評論家がいなくても困る人はいないけど、ごみ収集の人がいなければたちまち皆生活に困る」。 わかりやすく言えばこのひと言。生きる原型。
生活に欠かせない業務を引き受けてくれている人たちへ相応の報酬が支払われることが、社会に必須とされる“公平”であり、英知だ。
現状の歪みを正すことができれば、間違いなく社会は大きく飛躍するだろうけれど。
第一産業に重きを置くのは公平を通り越して崇拝に近いものがある。なくてはならない、生きる“原型”の方策なので。
「令和の米騒動」の火がチロチロと...。
軍事費増大による課税。年々積み重なって、かの国は革命にまで至ったけれど。
ともあれ、物価が元に戻りますよう、現在のところ神様にお祈りを。 大過ありませんように。お守り下さい。